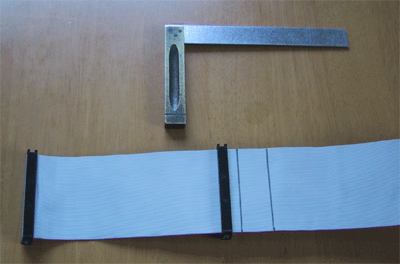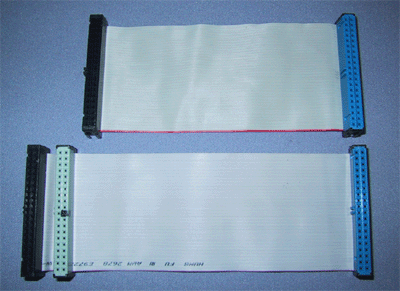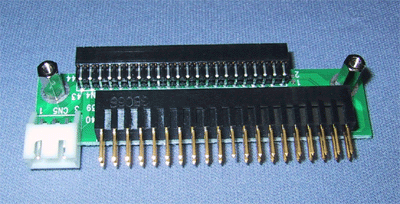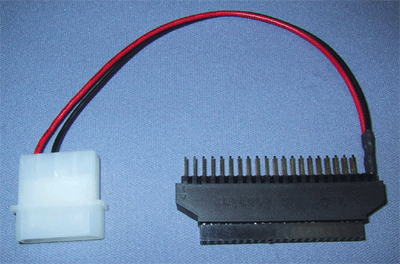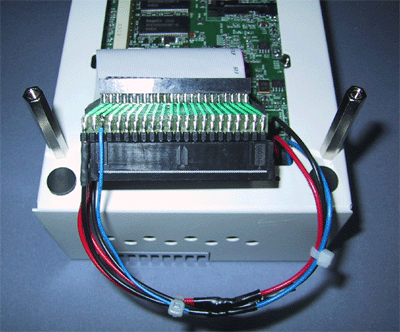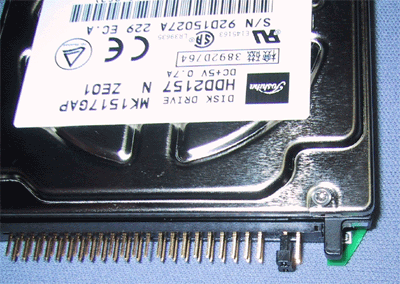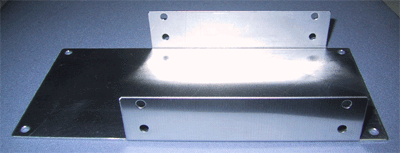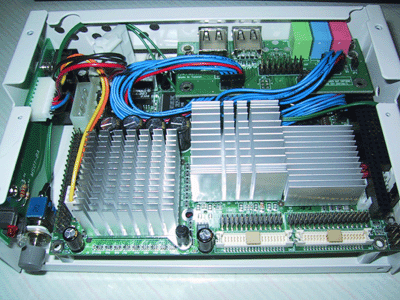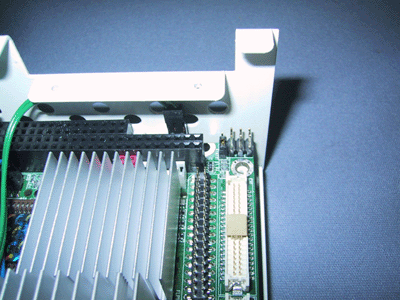| 1.2 最短IDEケーブルの製作(ATA/133対応 2台用) |
|
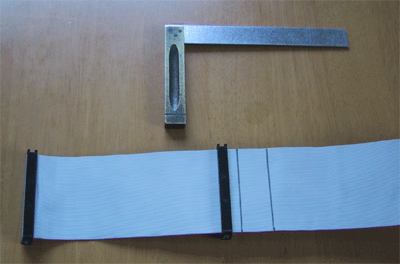 |
今回のハードウエアの準備ではこの作業が1番重要で、下手な作業をするとマザーやHDDを壊しかねません。
私は45cm程度のケーブルを購入して、それを全長137mmに改造しました。改造といっても
そんなに大袈裟なものでもありませんが、なにせ専用工具がないものですからその辺にあるものを使います。
青色のコネクタは残して灰色のコネクタ2個をマイナス調整ドライバーなどを使いはずす。
外したコネクターは再利用するのですからピンが抜けないよう慎重に。
直角定規を使いフラットケーブルに青色のコネクタから120mm,137mmの箇所にマジックで線を引く。
先程はずした灰色(黒)コネクターを線を引いた箇所にセットする。均一に力が掛かるようにつぶす。
万力等があればよいのですが、プライヤーでもなんとかできました。
2カ所ともできたら隣の信号線と短絡していないかテスター等でチェックして下さい。
(80芯タイプのIDEケーブルですから信号線の隣はGND線になります)
圧接が済んだらカッターナイフで余った部分を切り落とす。一気に切らないと切断面が汚くなります。
私は拘って137mmのIDE2台用ケーブルを作りましたしたが、自信のない方は既製品のまま使った方が安全です。
|
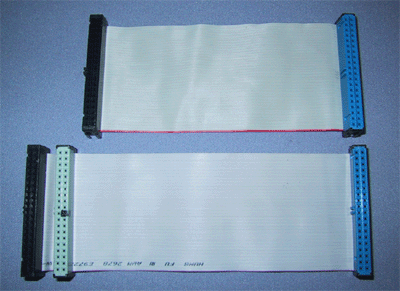 |
上は既設のIDEケーブル。
下は私が作った2台用のIDEケーブルです。 |
| 1.3 2.5インチHDDアダプター交換+追加 |
|
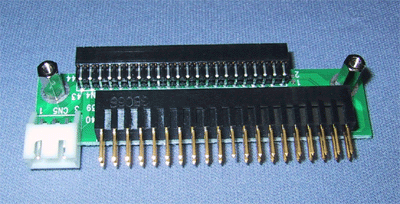 |
既設の変換アダプターはもったいないが撤去し購入した変換アダプターを使う。
0.3sqの赤、黒、青線は適当な所でカット |
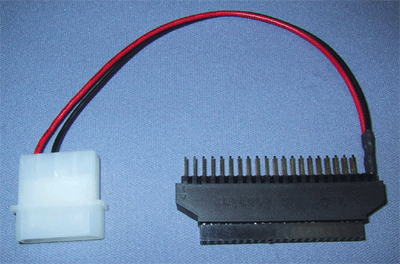 |
購入した変換アダプター
電源線は適当な所でカット |
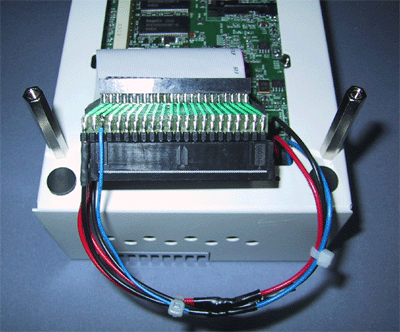 |
こんな感じに接続する。私は半田付けで接続し収縮チューブで保護しました。
赤は+5V、黒はGNDですからそのまま付き合わせるだけです。青線はHDDのアクセスLED駆動用ですから39番ピンに半田付けします。 |
| 1.4 2.5インチHDDマスター、スレーブ設定 |
|
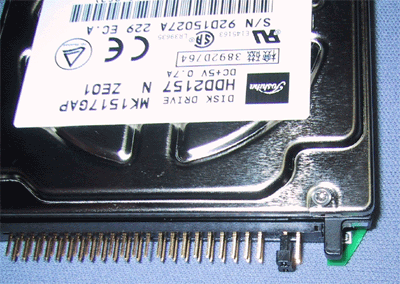 |
私が購入した東芝のハードディスクは写真のようにジャンパーする事でスレーブに、ジャンパー無しでマスターの設定でした。 |
| 1.5 特注金具 |
|
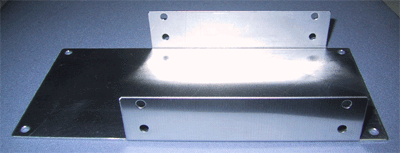 |
近くの板金屋さんに発注して作ったHDD取付金具(アルミ 1.0t)
発注図面
|
 |
近くの板金屋さんに発注して作ったカバー金具(アルミ 2.0t)
発注図面
|
| 1.6 マザーユーザーマニュアル |
|
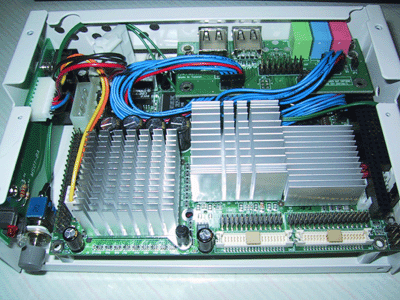 |
どうみても中身はEvalueのECM-3610(VIA Eden ESP6000)でしょ。OEMなんでしょうね。
http://www.evalue-tech.com/jp/evalueweb/products/specifications/model.cfm?mn=ECM-3610
ユーザマニュアルもダウンロードできます。
http://www.evalue-tech.com/jp/evalueweb/sns/downloadResults.cfm# |
| 1.7 ATATX1ジャンパ設定 |
|
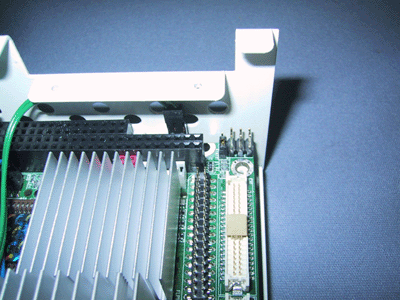 |
ユーザマニュアルからメーカー出荷時の間違いを見つけました。
私の購入したロット(2003/5/15着)ではATATX1ジャンパが1-2側の設定になっており、これが原因で自動的に電源OFFできなくなっていました。どんなOSを使ったってうまくゆくはずがありません。だってマニュアルによると1-2側はAT設定なんですから。おかげでdebian(カーネル)の設定を疑って2日程さまよってしまいました。普段馬鹿にしているWindows2000で試しても駄目だったのでハードを疑い発覚した次第です(^^;)
ジャンパーが正規な設定(2-3側 ATX設定)であればACPIをdisebleにした場合でも自動的に電源OFFできます。
|